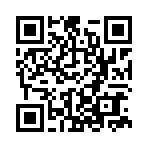2017年01月14日
住友重機械工業 5.56mm機関銃MINIMI 脱落防止
どうも‼︎
ASAHIです。
最近、富嶽隊Twitterの本格運用を開始しました。
フォローさんも結構増え順調です。
皆さんも良ければフォローしてみて下さい。
https://twitter.com/fugaku2010
そして、今日は大学入試センター試験1日目ですね〜
そう言や自分も受けました。
私の場合はセンター試験を受ける前に既に公募制の推薦入試で1校合格が決まっていたのであまりセンター試験に力入りませんでしたww
当時はクラスメイトに羨ましいがられ、そして、妬まれたのも覚えています。
と、言っても私立大学の公募制の推薦入試なのであまり賢い大学では無いのですが、皆んなは''受かった''事に対して羨ましがってた様です。
私が行ってた学校は中高一貫の某名ばかり進学校なのですが、その中でも底辺だった私からすると、有名国公立大に合格がした友人の方がはるかに羨ましいです。
高校時代、私は航空自衛隊の航空学生をかなり本気で目指していました。
ささやかな自慢ですが、某FPSの戦闘機の結果が世界ランキング5位に入った事もあり、某戦闘機ゲームもほぼ無敗で、博物館で実際のパイロットも訓練で使用した航空機のシュミレーターをした際には操縦を指導してくれた空自OBの方から航空学生を勧められた程です。
それぐらい空自のパイロットを目指していたのですが、無理でした。
理由は頭が足りなかった訳でな無く、色覚異常と極度の貧血です。
あの時はかなり落ち込みましたね〜
パイロットになると言う幼稚園の頃からの夢が身体的理由により絶たれてしまった訳ですから。
それに加え、どうにか航空機関連の職業に就きたいと思い、国土交通相航空保安大学校を受験したのですが、そちらも不合格でした。
1次試験は無事通ったのですが、2次試験の身体検査で極度の色覚異常と判断され、不合格になりました。
私の場合、2次試験は身体検査の後に面接試験が有ったのですが、身体検査が終わった後に個別に呼び出され、合格は厳しいと言う旨を伝えられました。
面接試験を受ける前に不合格を言い渡された時は正直心が空っぽになりましたね〜
いや〜
航空保安大学校に色覚異常検査が有るのは知っていたのですが、まさか色覚検査で落ちる程自分の色覚に異常が有るとは思いもしませんでした。
単色はちゃんと見分けられてるのですが、複合色になると弱い様です。
ですので、ASAHIの記事では色に関する記述はあまり当てにしないで下さいねw
まあ、色々有って今の私に至ります。
こうして、工学を志してるのも何かの縁かも知れません。
それもこれも、今となっては良い思い出です。
さて、本日は前置き&私の個人的な昔話が長くなり過ぎてしまいましたが本題に参りましょう。
本日は5.56mm機関銃MINIMIの脱落防止についてです。
後、各部部品の名称については部隊などで呼び方が異なるので参考程度にお願いします。

89式小銃の脱落防止は色々紹介されていますが、5.56mm機関銃MINIMIの脱落防止はあまり紹介されてなかったので紹介しようと思います。

まずは、被筒部の脱落防止です。
写真の様に下部被筒止め軸(ハンドガードピン(矢印の部分))お覆う様にして上部被筒(放熱被筒とも言う(ヒートカバー))を一周させます。
古い個体などはこの下部被筒止め軸が良く取れるらしいです。

こんな感じです。
その時に、


二脚部(バイポッド)が収まる様にテーピングするのがコツです。


握把(グリップ)は89式小銃と同じ様に脱落防止します。


提げ手止め軸(キャリングハンドルピン)も脱落防止します。
脱落防止しないと、時たま取れてしまう様です。

尾筒止め軸(ブリーチピン(ストックピンとも言う))の脱落防止です。
リングに通してから、

上からもう一度巻きます。

その際にビニールテープが遊底覆い(フィードカバー)にかからない様に注意して巻きましょう。

遊底覆い止めかん(フィードカバーピンのEリング)も脱落防止をします。

そして、こちらの遊底覆いネジ(フィードカバーネジ(左矢印の部分))と遊底覆いプラグ(こちらの呼び方はあやふやです(右矢印の部分))を脱落防止します。
画像の銃は2年前の伊丹駐屯地記念式典で撮影した実銃の5.56mm機関銃MINIMIです。
エアガンには前部のネジは無いので感じだけでもやっておきます。


こんな感じでしょうか?
こんなんじゃ取れるんじゃね?
と、おもう方も居るかも知れませんが、そんな事気にしちゃいけません。
やる事に意味がありますw

次はこちらです。
矢印の部分を脱落防止をします。
こちらの画像も伊丹駐屯地にて撮影した実銃の5.56mm機関銃MINIMIです。
このピンの名前は、引き金室部止め軸とでも言うのでしょうか?
こちらも呼び名を聞いた事が有りません。
引き金室部止め軸と言うなら恐らくトリガーピンで間違い無いと思います。
エアガンではこのピンは再現されていません。
こちらも型だけやっておきます。


こちらも、すぐに取れてしまいますが、気にしてはいけません。


防塵蓋(ダストカバー)の脱落防止です。
89式でも、ダストカバーはダストカバーと呼ばれているのでわざわざ防塵蓋と言わなくても良いかも知れません。
こちらはダストカバーが動く様にテーピングすればそれで大丈夫です。


全体はこんな感じです。
何度も言いますが、脱落防止をするだけで本当にリアルさが増します。


89式小銃と並べてみるとこんな感じです。
やっぱり自衛隊の銃は良いですね〜
私達に一番身近な銃が一番ですw
以上です。
ありがとうございました。
質問等あれば気軽にコメントして下さい。
ASAHIです。
最近、富嶽隊Twitterの本格運用を開始しました。
フォローさんも結構増え順調です。
皆さんも良ければフォローしてみて下さい。
https://twitter.com/fugaku2010
そして、今日は大学入試センター試験1日目ですね〜
そう言や自分も受けました。
私の場合はセンター試験を受ける前に既に公募制の推薦入試で1校合格が決まっていたのであまりセンター試験に力入りませんでしたww
当時はクラスメイトに羨ましいがられ、そして、妬まれたのも覚えています。
と、言っても私立大学の公募制の推薦入試なのであまり賢い大学では無いのですが、皆んなは''受かった''事に対して羨ましがってた様です。
私が行ってた学校は中高一貫の某名ばかり進学校なのですが、その中でも底辺だった私からすると、有名国公立大に合格がした友人の方がはるかに羨ましいです。
高校時代、私は航空自衛隊の航空学生をかなり本気で目指していました。
ささやかな自慢ですが、某FPSの戦闘機の結果が世界ランキング5位に入った事もあり、某戦闘機ゲームもほぼ無敗で、博物館で実際のパイロットも訓練で使用した航空機のシュミレーターをした際には操縦を指導してくれた空自OBの方から航空学生を勧められた程です。
それぐらい空自のパイロットを目指していたのですが、無理でした。
理由は頭が足りなかった訳でな無く、色覚異常と極度の貧血です。
あの時はかなり落ち込みましたね〜
パイロットになると言う幼稚園の頃からの夢が身体的理由により絶たれてしまった訳ですから。
それに加え、どうにか航空機関連の職業に就きたいと思い、国土交通相航空保安大学校を受験したのですが、そちらも不合格でした。
1次試験は無事通ったのですが、2次試験の身体検査で極度の色覚異常と判断され、不合格になりました。
私の場合、2次試験は身体検査の後に面接試験が有ったのですが、身体検査が終わった後に個別に呼び出され、合格は厳しいと言う旨を伝えられました。
面接試験を受ける前に不合格を言い渡された時は正直心が空っぽになりましたね〜
いや〜
航空保安大学校に色覚異常検査が有るのは知っていたのですが、まさか色覚検査で落ちる程自分の色覚に異常が有るとは思いもしませんでした。
単色はちゃんと見分けられてるのですが、複合色になると弱い様です。
ですので、ASAHIの記事では色に関する記述はあまり当てにしないで下さいねw
まあ、色々有って今の私に至ります。
こうして、工学を志してるのも何かの縁かも知れません。
それもこれも、今となっては良い思い出です。
さて、本日は前置き&私の個人的な昔話が長くなり過ぎてしまいましたが本題に参りましょう。
本日は5.56mm機関銃MINIMIの脱落防止についてです。
後、各部部品の名称については部隊などで呼び方が異なるので参考程度にお願いします。

89式小銃の脱落防止は色々紹介されていますが、5.56mm機関銃MINIMIの脱落防止はあまり紹介されてなかったので紹介しようと思います。

まずは、被筒部の脱落防止です。
写真の様に下部被筒止め軸(ハンドガードピン(矢印の部分))お覆う様にして上部被筒(放熱被筒とも言う(ヒートカバー))を一周させます。
古い個体などはこの下部被筒止め軸が良く取れるらしいです。

こんな感じです。
その時に、


二脚部(バイポッド)が収まる様にテーピングするのがコツです。


握把(グリップ)は89式小銃と同じ様に脱落防止します。


提げ手止め軸(キャリングハンドルピン)も脱落防止します。
脱落防止しないと、時たま取れてしまう様です。

尾筒止め軸(ブリーチピン(ストックピンとも言う))の脱落防止です。
リングに通してから、

上からもう一度巻きます。

その際にビニールテープが遊底覆い(フィードカバー)にかからない様に注意して巻きましょう。

遊底覆い止めかん(フィードカバーピンのEリング)も脱落防止をします。

そして、こちらの遊底覆いネジ(フィードカバーネジ(左矢印の部分))と遊底覆いプラグ(こちらの呼び方はあやふやです(右矢印の部分))を脱落防止します。
画像の銃は2年前の伊丹駐屯地記念式典で撮影した実銃の5.56mm機関銃MINIMIです。
エアガンには前部のネジは無いので感じだけでもやっておきます。


こんな感じでしょうか?
こんなんじゃ取れるんじゃね?
と、おもう方も居るかも知れませんが、そんな事気にしちゃいけません。
やる事に意味がありますw

次はこちらです。
矢印の部分を脱落防止をします。
こちらの画像も伊丹駐屯地にて撮影した実銃の5.56mm機関銃MINIMIです。
このピンの名前は、引き金室部止め軸とでも言うのでしょうか?
こちらも呼び名を聞いた事が有りません。
引き金室部止め軸と言うなら恐らくトリガーピンで間違い無いと思います。
エアガンではこのピンは再現されていません。
こちらも型だけやっておきます。


こちらも、すぐに取れてしまいますが、気にしてはいけません。


防塵蓋(ダストカバー)の脱落防止です。
89式でも、ダストカバーはダストカバーと呼ばれているのでわざわざ防塵蓋と言わなくても良いかも知れません。
こちらはダストカバーが動く様にテーピングすればそれで大丈夫です。


全体はこんな感じです。
何度も言いますが、脱落防止をするだけで本当にリアルさが増します。


89式小銃と並べてみるとこんな感じです。
やっぱり自衛隊の銃は良いですね〜
私達に一番身近な銃が一番ですw
以上です。
ありがとうございました。
質問等あれば気軽にコメントして下さい。
TSG トリプルセクターギア
FN F2000 比較レビュー
G&G FN F2000 レビュー
CyberGun FN F2000 Tactical レビュー
CyberGun FN F2000 Tactical 開封レビュー
Quality Power(ZL) DSA SA58 レビュー
FN F2000 比較レビュー
G&G FN F2000 レビュー
CyberGun FN F2000 Tactical レビュー
CyberGun FN F2000 Tactical 開封レビュー
Quality Power(ZL) DSA SA58 レビュー